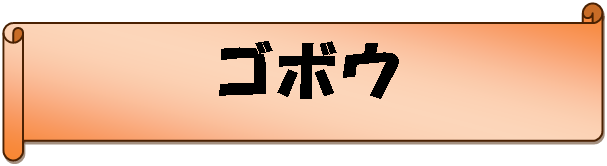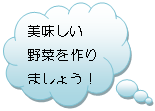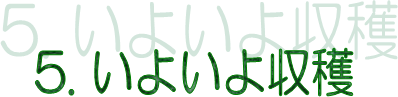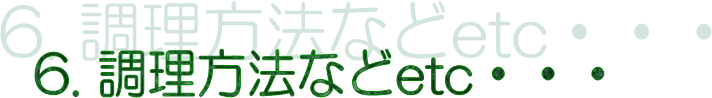|
�@ |
��܂� |
�A���t�� |
��C���̐A���t�� |
���n |
||||||||||||||||||||
|
�� |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||
|
�S�{�E�i�t�j |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�S�{�E�i�H�j |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�t�܂��@��܂��c�c4���` 5����{ ���n10���`2��
�H�܂��@��܂��c�c9���`10����{ ���n�@6���`8��

![]()
![]()

�S�{�E�́y�L�N�ȁz�̍���ł��B
�n���C���݂��琼�A�W�A�����Y�Ƃ����H���@�ۂ����Ղ�̖�ł��B
���{�ւ͒�����������炳��A��������ɂ͂��łɍ͔|�������Ȃ��Ă����悤�ł��B
20������25���̋C��ł悭����߁A�t��H�Ɏ���܂��~�⏉�ĂɎ��n����܂��B
���ĂɎ��n�����V�S�{�E�͏_�炩���T���_�ɍœK�ł��B
�~�̃S�{�E�͎ϕ��Ȃǂ����������ɂ��o�ꂵ�܂��B
�����ł͊�����Ƃ��Ĉ�����قljh�{���������A�H���@�ۂ��Ƃ��Ă��L�x��
�֔��咰�K���̗\�h�ɂ����ʂ�����V�R�̌��N�H�i�Ƃ�����ł��傤�B
��Ȑ���
Ø �����̂Ȃ������ꂢ�ɂ����s�n���H���@��
Ø �̑��@�\�����ߑ̓��őf��r�o�������n���H���@�ۃC�k����
Ø ���{���s���ʂ̂����A���M�j��
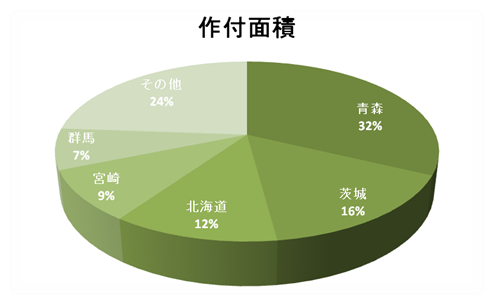
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�F�_�ѐ��Y�ȓ��v(����23�N�Y)
�S�{�E�͂�������̕i�킪���肻�ꂼ�꒷���⑾���A�H�ׂ��镔���Ȃǂ��قȂ�܂��B
���̒���������̓X�[�p�[�Ȃǂł��悭��������S�{�E�ł��B
���̒Z���Z����͑������������̂������A���܂�[���Ƃ���܂ōk���Ȃ����ň�Ă�ꍇ�ɕ֗��ł��B
�܂��v�����^�[�͔|�ł͍��̒�����30�`40cm���̃~�j�S�{�E���K���Ă��܂��B
�傫�ȃS�{�E���A�N�����Ȃ��̂ŃT���_�����ł��B
���ɂ��H�܂��ō͔|�ł���t�S�{�E�i�Ⴂ�t���ƍ����H�ׂ���j�Ȃǂ�����܂��B
��Ă�ꏊ��G�߂ɂ���ĕi���I�ԂƂ悢�ł��傤�B
������
l ����咷�c�t�B�V���L�V���L�����������ƓƓ��̍���ł��B
l ���엝�z�c�t�E�H�B�����ŁA���������炩���č���ɕx�ݐH����������Ă��܂��B
l �R�c�����c�H�B�������k���ł��炩���A����ɕx�ݔ��͔����Ċ��炩�ŃX�̓�����x���ł��B
l ���Ȃ������c�t�B����80cm�O��ŁA��[�܂œ��t���悭���`�E�����Ƃ��ɗǂ������܂��B
�Z����
l ��Y���S�{�E�c�t�B�����Z�\�Z���`�قǂ̑����Z���S�{�E�ł��B
l �~�j���ڂ��c�t�B�t�܂��͔|���嗬�ō����Z���i�킪�嗬�ł��B
l �T���_�ނ����c�t�B����35�`45cm���x�̒Z�����S�{�E�ł��B�d���100�����x�Ŏ��n�ł��܂��B
��͎��ɔ���}���������܂܂�Ă��邽�߁A�A����O�Ɉꒋ��␅�ɐZ�����肵�₷�����Ă����܂��B
�܂��엀�̓y��[���k���Ă����܂��B
���͔|
l ��y�ΊD(1�u������100g���炢)�@�y�̎_���𒆘a����B
l ��ؐ�p�엿�B
�v�����^�[�͔|
l �v�����^�[�┫�A�܂��͔|�{�y��엿�������Ă����܁i���͂����ӁA�[����40c���ȏ゠����́j�B
l ��ؐ�p�̔|�{�y�i�������j�B
l ��ؐ�p�엿�B
 ���y����
���y����
���͔|
�S�{�E�� �_���Ɏキ�_���y������ �̂ŁA�ƒ�؉��ɂ� ��y�ΊD���܂��Ă悭�k���_���𒆘a����悤�ɂ��܂��傤�B
�S�{�E�͂��̑��̖�Ɣ�ׂĂ��Ȃ�[�߂ɍk���āA�ҍ���\�h���邽�߂ɐ₲�݂����C�悭��菜���悤��
���ĉ������B
��܂���2�T�ԂقǑO�܂łɋ�y�ΊD�⊮�n�͔��y�S�̂ɉ����A�y�̐����𒆘a�����Ă����܂��B
��y�ΊD��1�u������100g���炢�A���n�͔��1�u������3kg���ڈ��ł��B
�������A���t��������1�T�ԂقǑO�ɍ���10�`30cm��30cm�قǂ̑傫���̐������A���̐^��
�[��40cm�قǂ̍a���@��܂��B�a�̒��ɖ�ؐ�p�엿�����A�y��߂��Đ��𐮂��܂��B
���S�{�E�͘A�삪���Ȃ̂ŁA�L�N�Ȃ̐A����A�����ꏊ��5�N�قǔ����Ă��������B
�v�����^�[�͔|
�p�ӂ��Ă������v�����^�[�ɖ�ؐ�p�̔|�{�y�����܂��B
�|�{�y��엿�̑܂ō͔|����ꍇ�́A���͂����悭���邽�ߑ܂̒�Ɍ����J��
��ɖ�ؐ�p�̔|�{�y�����Ă��������B
����܂��E�A���t��
�S�{�E�̎�܂��́A�t�i4�`5���j�������͏H�i9�`10���j�ɍs���܂��B
��̏�Ԃ�15���ȉ��̋C���ɂ��炵�Ă��܂��Ɖ肪�o�ɂ����Ȃ�܂��B
�܂��S�{�E�������������ɑ����~��Ă��܂��ƁA�S�{�E�������オ�����菝�����肵�܂��B
�C����20�`25���̒g���������ɐA���Ĉ�Ă܂��傤�B
�H�܂��͔̍|�ł͏t�܂��͔̍|�����n���Ԃ��Z���Ȃ�A�Ƃ������Ȃǂ��N����₷���ł��B
�H�܂������̕i���I��ň�Ă�Ƃ悢�ł��傤�B
�@���S�{�E�͒n�ʂɏo�Ă��镔���͊����Ɏキ�A3���قǂŗt��s���͂�Ă��܂��܂��B
�������n���[���ɖ��܂��Ă��鍪�̕����͊����ɋ����A�|20���ł������Ă����܂��B
��܂����s���O�̓��ɁA�y�ɐ��������Ă����܂��B
��܂��̓����A���������2�`3cm���炢�̐[���̌���5�`15cm�قǂ̊Ԋu���Č@���Ă����܂��B
���v�����^�[�͔|�̏ꍇ�A�Ԋu��5�`8cm�قǂɂ��܂��傤�B
�@��������2�`5��������܂��A5mm�`1cm���x�̓y�Ŕ���������ʼn������܂��B
���S�{�E�̎�͌����D�ނ̂ŁA�y�������߂��Ȃ��悤�ɂ�����܂ł͓y���������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
�������
�����͐����̓x�����ɂ���ĕp�x���قȂ�܂��B
�����������͊����Ɏア�̂œy�̕\�ʂ����������ɁA���̓s�x���������܂��B
�{�t��10���قǂ��đ傫���Ȃ�Ƌt�Ɏ��C�Ɏキ�Ȃ�A
2���ȏ㑱���Đ���^���Ă��܂��ƌ͂�Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ŋC�����܂��傤�B
���ǔ�E�y��
�S�{�E���ǔ�͌㔼�̐�������2��s���̂���ʓI�ł��B
1�x�ڂ͖{�t��3�`4���ɂȂ������̊Ԉ�����Ƃ̌�ɍs���܂��B
�엿��c���炠����x���ꂽ�Ƃ���i���̎���Ȃǁj�ɂ܂��ēy�����܂��傤�B
�ǔ���s���Ƃ��́A�엿�̂��������ŃS�{�E���͂炵�Ă��܂�Ȃ��悤���ӂ��܂��傤�B
�y����Ƃ��͐������Ă��镔���߂Ă��܂�Ȃ��悤�C�����܂��B
2�x�ڂ͖{�t�̐���10���قǂɂȂ葐�䂪30cm�قǂɂ܂Ő����������ɍs���܂��B
1�x�ڂƓ����菇�ōs���܂��傤�B
���Ԉ���(�肩���E�E�c)
����܂��Ă���10���`2�T�ԂقǂŔ��肵�܂��B
�{�t��1�`2���o������A�t�̐F�����������̂⌳�C�̂Ȃ����̂𒆐S�ɊԈ������܂��B
�{�t��3�`4���ɂȂ�������A�炿���������̂�t�Ɉ炿���悷���č����n��ɏo�Ă��܂������́A
�t���܂����������Ă��炸���ɍL�����ĐQ�Ă���l�Ȃ��̂��Ԉ�����1�J������1�{�̃S�{�E������
�����Ă���悤�ɂ��܂��i1�{���āj�B
�Ԉ����Ƃ��͎c���Ă����S�{�E�������オ��Ȃ��悤�ɁA�S�{�E�̍�������ʼn������Ȃ���s���܂��傤�B
�t�����ɍL�����Ă�����̂́A�S�{�E���ό`���Ă���\���������ł��B
���a�C�E�Q��
��ȕa�C�ɂ͍����ەa�₤�ǂa�A������a�Ȃǂ�����܂��B
�a�C�ɂ������Ă��܂�������͂ɓ`������O�ɁA��U�z�⊴�������̏����Ȃǂ��s���A�v���ɑΏ����Ă��������B
�����ەa�Ȃǂ́A�����ӂ̕��ʂ����悭���邱�Ƃŗ\�h���邱�Ƃ��ł��܂��B
���ǂa�̓J���엿�i����͔̍|�ɓK���������엿�j���\���Ɏ{�����ƂŖh���܂��B
������a���A�������ēy���ɐ��������߉߂��Ȃ��悤�ɂ��܂��B
�S�{�E��A����O�ɂ�������Ƌ�y�ΊD���ɂ܂����ƂőΉ��ł��܂��̂Ŏ����Ă݂܂��傤�B
�܂��A���܂ɂł����A�u�����V��g�E���V�A�l�L�����V�Ȃǒ������Ă��܂����Ƃ�����̂Œ��ӂ��ĉ������B
�A����s���Ă��܂��Ɛ����ނ̔�Q�ɑ������肵�܂��B
�����o�Ă��܂����ꍇ�͑��}�ɋ쏜���܂��傤�B
�E�������������鑐���i�}���[�S�[���h�Ȃ��j���ꏏ�ɐA����Ƃ悢�ł��傤�B
���͔|�@
�S�{�E�͍ŏ��̐������x���̂ŁA�G���Ȃǂ�����ɐ�����Ɨ{��������炿�������Ȃ�܂��B
�G���͌������摁�߂Ɏ�菜���܂��傤�B
[�܍͔|�Ɣg�͔|]
�S�{�E�͒n���[���ɂ܂ō���L�����n�Ɏ�Ԃ�������܂��B
�|�{�y��엿�������Ă����܂�n�\�ɂ����āA���̒��ō͔|����Ǝ��n�����₷���Ȃ�܂��i�܍͔|�j�B
���@�Ƃ��ẮA�܂��͔|�ꏊ�̒n�ʂ��k�����̏�ɒ������ʂ��ēy����ꂽ�܂�u���A���̓y�Ɏ���܂��Ă��������B
���n����Ƃ��͑܂�j��S�{�E�̎���̓y������ȒP�Ɏ��n�ł��܂��B
�܂��n���ɔg�߂��̏�ŃS�{�E���͔|����ƁA�ɉ����悤�ɃS�{�E���������Ă����̂ŁA
���n�����₷���Ȃ�܂��i�g�͔|�j�B
�g���g�p����ۂɂ́A��20���̊p�x�Œn���ɖ��߂܂��傤�B
 ���͔|
���͔|
�t�Ɏ�܂����s�����ꍇ�͖�6������̏H���A�H�Ɏ�܂����s�����ꍇ�͖�9������̏t����
�������a2cm���炢�ɂ܂ő����Ȃ�A�t���͂�n�߂܂��B
�����Ȃ�����Җ]�̎��n�����ł��B
���n�ł��n�߂�2�����Ԃ��炢�����n���� �ɂȂ�܂��B
�������͍���1�`1.5cm���炢�̑����̎��ɑ��߂Ɏ��n���A��S�{�E�Ƃ��Ċy����ł��悢�ł��傤�B
���n�́A�܂��t������������15cm���x�c���ď㕔����������܂��B
�S�{�E�������Ă����O�̒n�ʂ�80cm�قǂ̐[���܂Ō@��A�c���Ă������t����������
�@�������̕����ɓ|���悤�ɂ��Ȃ�����������܂��B
�S�{�E�͊�������ƍd���Ȃ� �̂ŁA���n��������̃S�{�E���������Ȃ��悤�ɋC�����Ă��������B
�����ԕۑ�����ꍇ�͓y�̒��ɖ��߁A�y���̂܂��点���V�����ɕ��|���܂ɓ���
��Ï��ɏc�u���ɂ��Ē�������Ȃǂ��Ă��������B
�������߂���ƃX����i���ɋ⌊���ł����ԁj�̃S�{�E�ɂȂ�܂��B���̎�����ڈ��Ɏ��n���I���Ă��������B
�v�����^�[�͔|
�~�j�S�{�E�̏ꍇ�͎���܂��Ă�����70�`100���O��o��
������1�`2cm���x�ɂȂ�H���ƂȂ���n�̎����ł��B
�����������Ĉ��������Ď��n���܂��傤�B
�������߂Ɏ��Ə_�炩���S�{�E�����n�ł��A����w�T���_�����ƂȂ�܂��B
�����̃S�{�E��A�����ꍇ�͑�����1cm���x�ɐ�����������Ŏ�̂肵�܂��傤�B
 �����O�ɃA�N���������邱�Ƃ���ʓI�ȃS�{�E�ł����A
�����O�ɃA�N���������邱�Ƃ���ʓI�ȃS�{�E�ł����A
���͂����A�N�����̎��ɐ�������������̂́A�A�N�ł͂Ȃ�
�S�{�E�Ɋ܂܂�� �h�{�f�̃|���t�F�m�[�� ���Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��B
���̉h�{�f�����ɗn�������Ă��܂��ŁA�h�{�ʂ��炢�����܂�A�N�����͂��Ȃ����������悤�ł��B
�������A�G�O���Ȃǂ��C�ɂȂ�ꍇ������܂��̂œ��ɐ��ŐH�ׂ�Ƃ��ɂ͓K�x�ɐ��ɂ��ăA�N���������܂��B
����҂炲�ڂ���T���_�A�{���ڂ��������݂��тȂǂɂ���ƐH���╗�����y���߂܂��B
<�g�b�v�y�[�W>�ֈړ�����